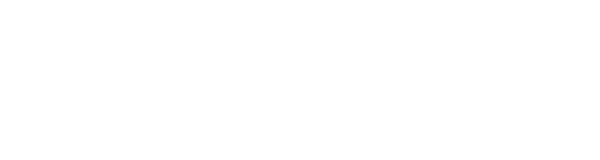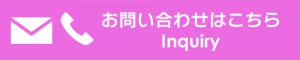Q : 左の胸の下あたりがギューっと痛くなることがあります(63歳女性)

A:胸の痛みはホント心配ですよね。胸から胃にかけて丁度みぞおちのあたりを専門的には心窩部と言いますが、このあたりが痛くなって気になる場合、痛みの具合や続き方にもよりますが、一度医療機関への相談をお勧めします。
特にすぐに対応が必要なのが狭心症や心筋梗塞、心筋炎や心膜炎です。 これらは心臓に十分な血液が供給されないため、心臓の筋肉や包み込む膜に異常が起こることで痛みが起こります。数分以上続く場合、冷や汗が出る場合、初めてでわからない場合などは、すぐに消防や医療機関に相談してみてください。また、みぞおちからお腹の上の方では消化器系の問題の場合もあります。胃潰瘍や逆流性食道炎では胃酸が食道に逆流することでいわゆる”胸やけ”や刺すような痛みを引き起こすことがあります。また、胆嚢に問題がある場合では肝臓のある側、右側に痛みが出ることが多いですが、左側にも広がることがあります。その他にも肋間神経痛や腹筋の痛みだけでなく、ストレスに対する反応や不安感などが原因で、胸の痛みを感じることもあります。
いずれの原因にしても、初めてこのような痛みが起こる場合や、時間が長く続くもの、頻繁に起こる場合や、他の症状(息切れ、めまい、吐き気など)を伴う場合は、医療機関に相談、受診しておくことをお勧めします。
日常生活で出来る予防法としては、食事、運動、睡眠、禁煙、適度な飲酒、ストレス対策が重要です。バランスの取れた食事を心がけ、ビタミンや繊維の豊富な野菜、果物、全粒穀物、そして加工の少ない、ささみなどの低脂肪のタンパク質、新鮮な魚やオリーブオイル、えごま油などの質の良い油もお勧めです。また、味付けも注意が必要です。過度な塩分、脂肪分や糖分を控えることで、心臓病や消化器系の問題を予防できるでしょう。週に150分以上の中等度の有酸素運動(ウォーキング、サイクリングなど)を目指しましょう。筋力トレーニングも体力に合わせて、週に2回以上取り入れると好ましいでしょう。喫煙は心臓病や呼吸器系の病気のリスクを高めます。気になる人はいつでもぜひ、禁煙を始めてみましょう。アルコールの摂取は適度に抑えましょう。女性は1日に1杯まで、男性は2杯までが目安です。そして睡眠、スポーツ選手や受験生のパフォーマンスが向上するとして注目されています。ストレスを減らすためにリラクゼーション法としてストレッチ、入浴、ヨガ、瞑想などと併せて睡眠時間や睡眠環境を大切にしましょう。また、定期的に健康診断を受けることも大切です。自治体や会社からのお知らせに従って受けてください、受けた結果で再検査や要精査の判定があれば、結果をを放置せず医療機関で相談しましょう。
以上胸の痛みについてはまとめてみました。症状を軽視せず、自分を過信せず、適切なタイミングで医療機関を受診してくださいね。併せて日常的な健康管理と疾病予防を続けること(いったんやめてもいいので、また再開すること)がとても大切です。
啓和会では地域の専門医療機関と連携し、地域の皆様の健康を医療と介護の融合で支えてまいります。ぜひお気軽にいらしてください。
参考情報
Mayo Clinic:
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/heart-disease-prevention/art-20046502
厚生労働省:
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-005.html
世界保健機関 (WHO):
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)