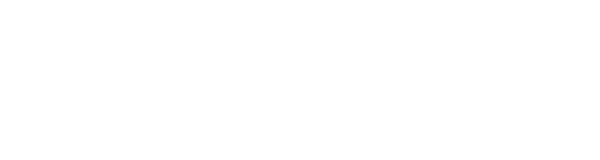Q : 時節柄でしょうか、気が落ち着かず眠れません。ストレスは感じていますがどうしたらよいでしょうか?(32歳女性)
A : 30歳代は、職場環境や人間関係にも慣れて日常生活も軌道に乗るといわれる頃。周囲からの期待もあるのではないでしょうか?病気や家族・友人との出来事など沢山のことがストレスの原因になっていることでしょう。身体だけでなくメンタルの健康も当然心配になってきますよね。今回ご紹介するストレスへの対応が、一筋縄ではいかないこの時代をみんなで生き抜く一助になれば幸いです。
ストレスとは、もともと物理学の専門用語で、物体の外側からかけられた力によって歪みが生じた状態を言います。一方、普段私たちが「ストレス」と言っているものは、「心理・社会的なストレスの源、ストレッサー」のことを指しています。職場や家庭など生活のありふれた場面で、仕事や家事の作業や対人関係などの要因がストレッサーとなり得ます。これらによって引き起こされるストレス反応はポジティブ、ネガティブの2つに分類でき、更に心理面、身体面、行動面の3つに分けることができます。
例えば、集中力の向上、楽しさや活気の上昇、高揚感などのポジティブな心理反応に対して、活気の低下、イライラ、不安、抑うつ(気分の落ち込み、興味・関心の低下)などはネガティブな心理面での反応です。
身体面でのストレス反応には、力のみなぎる感じ、爽快感などのポジティブな反応から体のふしぶしの痛み、頭痛、肩こり、腰痛、目の疲れ、動悸や息切れ、胃痛、食欲低下、便秘や下痢に加えて不眠などさまざまなネガティブな反応があります。
また、単純作業における手際の向上、早めの睡眠や健康な食事や周囲の人への相談などのポジティブな行動変容も見られる一方で、逆にクリエイティブな業務における想像力や効率の低下、飲酒量や喫煙量の増加、仕事でのミスや事故、ヒヤリハットの増加などはネガティブな行動面でのストレス反応も見られます。
ストレスに対処する行動としては、ストレスそのものに働きかけてストレスをなくしてしまう根本的な方法や、自分自身の工夫や周囲への相談、ルールの変更などでストレスへうまく対応して解決する方法、さらにストレスによって発生した自分の不安感や怒りなどの感情を周囲の人たちに聴いてもらい上手に発散する方法などがあります。日頃からストレスが発散できるよう、趣味や生きがいとなるものを持つことや、なにかと協力してもらえる人間関係も重要となります。
自分自身でできる対処行動として大切なのは、まずストレスを受けている自分に気づく(気づいてもらう)ことです。そしてそのストレス反応が頭痛・動悸・不眠・飲酒増加・ヒヤリハットであることを知っておくことが有効です。もし自分や周囲の人が不安やイライラ、活気の低下、興味関心の低下にとらわれていることに気づいたら、その状態を責めることなくネガティブな感情から立ち戻り、最も大切な生きがいに沿って行動すること、意識的に周囲の人に親切にすること、呼吸法や瞑想、マインドフルネスなどネガティブな感情を和らげる方法をみんなで試してみましょう。時間をかけても練習する価値のある、あの世界保健機関WHOお墨付きの方法です!
質問者様は眠れず困っておられるようですね。睡眠も質と時間が重要です。まずは飲酒や夜のスマホなどを控えて、ストレッチやヨガなど適度な運動やリラクゼーションで睡眠の質を上げてみませんか?十分な睡眠がストレスからの回復には重要です。人にもよるようですが、個人的には3時間程度の仮眠ではなく、6、7時間程度の十分な睡眠時間をお勧めしています。作業の効率や気分にも良い影響がみられますよ。繰り返しになりますが、自分で対応しきれないときは決して無理をせず周囲の人たちの協力も仰いで、よりよい解決の糸口を目指しましょう。窮地に陥った時に相談できる人を持ち、適切なケアを適切なタイミングで受けることは我々が健康で効果的な社会活動を続けるために極めて重要です。
ストレスは、私たちが生きていく上で避けることのできないものですが、うまく対応することができれば自分や組織の成長にもつながります。気づきと工夫、思いやりは我々が人生を豊かに送る助けになります。みんなでこのストレスフルな現代社会を乗り切ってゆきましょう!
当院内科外来は専門医療機関とも連携しながら介護と医療を融合して、地域の皆様の健康生活をサポートいたします。お気軽にご相談ください。(金崇豪)
◇厚生労働省 こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
HOME>ストレス軽減ノウハウ
https://kokoro.mhlw.go.jp/nowhow/nh001/
◇Doing What Matters in Times of Stress: World Health Organization
https://www.who.int/publications-detail/9789240003927
◇睡眠時間が翌日終日の認知・運動機能に与える影響
ITヘルスケア 2008 年 3 巻 2 号 p. 96-105