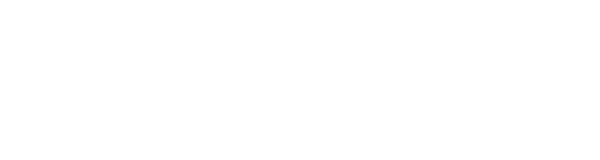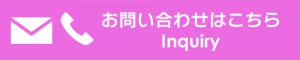Q : 特に何もしていないのに字を書こうとすると手がふるえることがあります(72歳女性)


A:日常では気にならないのに、ふとした折にきづく手の震え気になりますよね。手の震えにはどんな種類があり、どう対応したらよいのでしょう?
字を書こうとすると手が震えること、これは書痙、局所ジストニアなどと呼ばれることもあり、心理的な要因やシステムの異常など色々な理由で起こることがあります。熱心に一生懸命書こうとしたり、きれいな字を書かなければならないなどストレスを感じているとでやすいです。良い仕事をする時ほどまずは気分転換、リラックスして取り組む事をお勧めします。
一般的に、手の震えにはいくつかの種類があります。まず、生理的振戦と呼ばれるもので、普通のストレスや疲れで手が震えることがあります。これは誰にでも起こることで、特に心配はいりません。また、本態性振戦というものもあり、これは遺伝の影響があります。普段は震えないけれど、手を使うときに震えるのが特徴です。さらに、パーキンソン病や甲状腺の問題が原因で手が震える場合もあります。この場合は特別な治療が必要です。
では、どんな人が手の震えになりやすいのでしょうか。まず、ご年配の方です。お年を取ることで筋力の低下や神経のシステムに影響が出て、手が震えやすくなります。次に体質です。家族に手の震えの病気がある場合、その影響を受けることがあります。そして、特定の病気がある人も手の震えが出やすいです。例えば、パーキンソン病の人は安静にしていても手が震えることがありますし、甲状腺が過剰に働く甲状腺機能亢進症の人も同様です。また、神経の病気等、例えば小さな脳梗塞や多発性硬化症 (MS)等も手の震えから診断につながることもあります。さらに、一部の薬を飲んでいる人も手が震えやすいです。特に精神安定剤や抗うつ薬などの薬が原因となることがあります。アルコールやカフェインを多く摂る人も注意が必要です。長期間多量に摂ると手が震えることがあります。そして、ストレスや不安が多い人も手の震えが出やすいことがあります。
では、どうすれば手の震えを予防できるのでしょうか。まず、ストレスの原因と反応を調整すことが大切です。足湯やカフェで読書やおしゃべりなどリラックスする時間を持ち、深呼吸やストレッチ、好きな趣味を楽しむことを心がけてください。次に、バランスの良い食事を心がけましょう。繊維やビタミン、タンパク質など栄養バランスの取れた食事で体の調子を整えることができます。そして、十分な睡眠を取ることも重要です。長さだけでなく”良く寝たな”と感じる熟眠感を目安にしてみるとよいでしょう。さらに、適度な運動をすることも健康に良いです。無理のない範囲で運動習慣を取り入れることが大切です。
もし手の震えが気になる場合や症状が続く場合は、医療機関に相談することをお勧めします。病院では、まずいつ手が震えるのか、他にどんな症状があるのか、日常生活の中で困っていることは何かを聞かれることがあります。
啓和会では地域の皆様の”日頃の困った”に耳を傾け医療と介護のサービスで暮らしを支えてまいります。ぜひご相談にいらしてください。
参考】
手の震え 長寿医療研究センター 手の震え | 国立長寿医療研究センターhttps://www.ncgg.go.jp/hospital/navi/03.html
(症状編)ふるえ 日本神経学会
https://www.neurology-jp.org/public/disease/fuzuii_detail.html
Parkinson disease 世界保健機関
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/parkinson-disease
Essential tremorメイヨークリニック
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/essential-tremor/symptoms-causes/syc-20350534